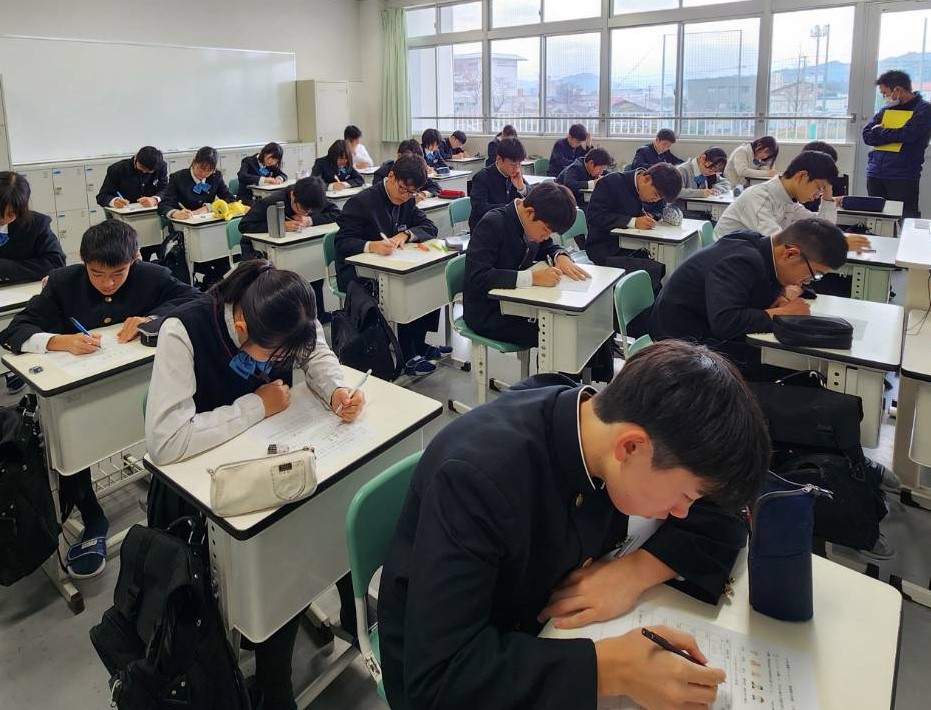中学校の道徳の授業風景
今日は道徳の授業風景を紹介します。
この日、中学1年生は「いじりといじめの違い」について、クラスみんなで考えました。
7種類のいじり(1対1のいじり、仲の良い者同士のいじり、暴力を伴ういじりなど)について、クラス全員で一つ一つ丁寧に検証しました。
「クラス一致でこのいじりは許される」という結論には至ったものはなく、人によって許せる境界線が違っていたことに気づき、いじりを介した人間関係構築ではなく、相手を尊重することによる人間関係を構築することの大切さを再認識したようでした。
「いじる」は漢字では「弄る」と書きます。
「弄ぶ(もてあそぶ)」という意味が含まれていることにも気づき、「いじり」も「いじめ」であることを再度学びました。
中学2年生は「価値観の相違」について学びました。1つのストーリーを読んだ後に、自分が共感できるモノの順位付けを行いました。
その後、小グループで共有し、級友と価値観が近いこともあれば、価値観が大きく違うことに気がついたようです。
授業では、「Seek First To Understand, Then To Be Understood.(理解に徹することで、理解される)」という言葉が紹介されました。
「日々、一緒に生活している仲間同士であっても価値観が違うことがあるのだから、歴史的・文化的背景がことなれば、当然、価値観も大きく異なって当然だよね。
だからこそ、相手を理解しようとする姿勢をもっておくことは大切なんじゃないかな。」という問いかけもありました。
中学3年生は「二通の手紙」を行いました。
動物園の入園係を務めていた主人公が、ある日、規則を破って保護者なしの幼い姉弟を入園させ、入園させた姉弟が閉園時間を過ぎても戻らず、結果、職員総出で捜索することに。
この姉弟は無事発見され、その後、姉弟の母親から感謝の手紙が届いたが、その一方で、上司からは停職処分の通知を受けたという話です。
「感謝の手紙」と「懲戒処分の通告書」という対比を通して、多角的な視点から規則の意味を考える時間になりました。
道徳の時間にどのようなことを考えたのか?
道徳の時間を経て、考えがどう変わったのか?
など、ご家庭での話し合ってもらえると、さらにより深い学びにつながると考えています。